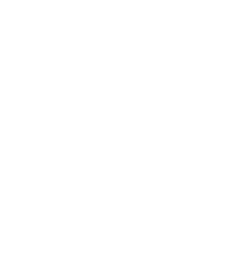言語学バーリ・トゥード Round 2: 言語版SASUKEに挑む
川添 愛 (著)
\各界よりコメント続々/
ことばの「なぜ?」に向き合う、爆笑必須エッセイ!
迷わず読めよ、読めばわかるさ
「自ら手傷を負いながら「あるある」の本質に肉薄する渾身の回をはじめ、今回のRound 2も楽しくて楽しくて。」
古田徹也氏(哲学者)
「笑えて、ためになり、読み終わるとフリーダムな気持ちになる奇跡の本。」
高野秀行氏 (ノンフィクション作家)
「前作も最高でしたが、今作も相変わらず川添節が炸裂しまくってる。まえがきの2pからボケの手数がすごすぎる。最高だ。」
水野太貴氏(ゆる言語学ラジオ)
【内容紹介】
レイザーラモンRGの「あるあるネタ」はどうしておもしろいのか。「飾りじゃないのよ涙は」という倒置はなぜ印象的なのか。猪木の名言から「接頭辞BLUES」まで縦横無尽に飛び回りながら、日常にある言語学のトピックを拾い出す。抱腹絶倒の言語学的総合格闘技、Round 2スタート!
【主要目次】
この本を手に取ってくださった皆様へ
1.生産者の顔が見える原稿
2.言語版SASUKEに挑む
3.言葉に引導を渡す者
4.あるあるネタはなぜ人を笑顔にしがち♪なのか
5.最高にイカすぜ、倒置は!
6.悪い言葉の誘惑
7.【コント】ミスリーディング・セミナー
8.2023年も“行けばわかるさ”
9.【創作】言語モデルに人生を狂わされた男
10.話題のAIをちょっと真面目に解説してみる
11.【創作】メトニミーのない世界
12.日本語は「世にも曖昧な言語」なのか
13.重言パラダイス
14.日本語は本当に「非論理的な言語」なのか
15.【コント】接頭辞BLUES
あとがき
著者について
【著者】川添 愛(かわぞえ・あい)
作家(言語学)
1973年生まれ。九州大学文学部言語学科卒、同大大学院にて博士号(文学)取得。2008年津田塾大学女性研究者支援センター特任准教授、2012年から2016年まで国立情報学研究所社会共有知研究センター特任准教授。専門は言語学、自然言語処理。主な著書は『白と黒のとびら』(東京大学出版会、2013年)、『精霊の箱(上・下)』(東京大学出版会、2016年)、『自動人形の城』(東京大学出版会、2017年)、『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』(朝日出版社、2017年)、『コンピュータ、どうやってつくったんですか? 』(東京書籍、2018年)、『数の女王』(東京書籍、2019年)、『聖者のかけら』(新潮社、2019年)、『ヒトのコトバ 機械の言葉』(角川新書、2020年)、『ふだん使いの言語学』(新潮選書、2021年)、『論理と言葉の練習ノート』(東京図書、2021年)、『世にもあいまいなことばの秘密』(筑摩プリマ―新書、2023年)。
出版社 : 東京大学出版会
発売日 : 2024/8/20
言語 : 日本語
単行本 : 240ページ
寸法 : 12.7 x 18.8 x 1.7 cm