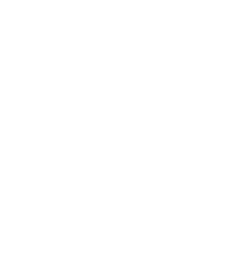【本と羊のロングセラー】死ぬまで生きる日記
「元気に暮らしているのに、理由なく“もう無理かも”が来る」——その“来かた”と“やり過ごしかた”を、著者がカウンセラーとの対話で丁寧に言葉にしていく記録です。
白黒つけないまま、グレーを抱えて進む。その姿勢に何度も救われました。感情に名前がつくと、息が少し楽になる。ページを閉じたとき、私は“治す”より“扱える”を選べるようになっていました。
しんどさの正体を身体感覚と言葉で捉え直すプロセスがわかる
「一人で頑張らない」ための依存先を増やす視点がもらえる
章末の読書リストは、落ちた夜の避難所マップみたい
日常は回っているのに、時々ふっと底が抜ける方へ。自己啓発では届かなかった場所に、静かに灯りをともす一冊です。
※心の不調に触れる内容を含みます。無理のないタイミングで、ゆっくりどうぞ。
土門蘭 (著)
日常生活はほとんど支障なく送れる。「楽しい」や「嬉しい」、「おもしろい」といった感情もちゃんと味わえる。それなのに、ほぼ毎日「死にたい」と思うのはなぜだろう? カウンセラーや周囲との対話を通して、ままならない自己を掘り進めた約2年間の記録。
著者について
1985年広島県生まれ。小説・短歌などの文芸作品や、インタビュー記事の執筆を行う。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』(寺田マユミとの共著)、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』、エッセイ『そもそも交換日記』(桜林直子との共著)がある。
出版社 : 生きのびるブックス
発売日 : 2023/4/20
言語 : 日本語
単行本 : 264ページ
「死ぬまで生きる日記」のレビュー・評価を要約してみました。
ご参考になればと思います
◉共感と自己理解
理由なく「死にたい」と感じる、楽しいことがあっても希死念慮が訪れる経験を持つ読者から、共感の声が多数寄せられている。
著者(土門蘭さん)のカウンセリングを通した自己理解の過程が、読者自身の自己理解を促すきっかけになっている。
◉カウンセリングの疑似体験
カウンセラーとの対話を通して内面を深く掘り下げていく内容が、読者にカウンセリングを疑似体験するような感覚を与える。
著者の感情や思考の詳細な言語化が、読者自身の感情をより深く理解する手助けとなる。
カウンセラーの寄り添う姿勢やアプローチが、読者に安心感を与えている。
◉感情の言語化
「死にたい」という感情を別の言葉(例:「帰りたい」「書きたい」)で表現することが、読者に新たな視点を与える。
感情を言語化することで、その根源にあるものに気づき、自己理解を深めることができる。
感情を言葉にすることで、気持ちが整理され、救われるという経験が共有されている。
◉生きづらさへの寄り添い
生きづらさを感じている人や苦しんでいる人に寄り添う作品として評価されている。
著者の苦悩のありのままの描写が、読者に共感と孤独ではないという感覚を与える。
「お守り」のような存在になると感じている読者もいる。
◉認知行動療法とマザーリング
カウンセリングで紹介された「認知行動療法」や「マザーリング」といった具体的な手法が、読者にとって役立つ情報として捉えられている。
特に「マザーリング」は、自分の感情を受け入れることの重要性を教えてくれると評価されている。
◉自己受容
ネガティブな感情を持つ自分自身を受け入れることができるようになったという読者の声が多い。
ポジティブ思考を強要するのではなく、ネガティブな感情も抱えながら生きていくことを肯定してくれる点が、多くの読者にとって救いになっている。
◉多様な解釈
読者の解釈は多岐にわたる。
自身の出自の葛藤や理想の母親像を求める気持ちと重ねて読んでいる人もいる。
著者と同じように「帰りたい」という感情を持つ人もおり、それぞれの経験や感情と照らし合わせながら読んでいることがわかる。
◉本の力
本を読むことで、不安が和らいだり、気持ちが少し楽になったりするといった体験が共有されている。
本との出会いは縁やタイミングであるという意見もあり、この本もまた、必要な時に出会うべくして出会った本であると感じている読者がいる。
総じて、「死ぬまで生きる日記」は、多くの読者にとって、共感、自己理解、そして心の癒しをもたらす作品として評価されています。著者の正直な言葉と、カウンセリングを通して変化していく姿が、読者の心に深く響いていると言えるでしょう。
土門蘭著書
歌画集 100年後あなたもわたしもいない日に
https://hontohitsuji.thebase.in/items/74160980
絵と短歌展図録「100年後」の7年後
https://hontohitsuji.thebase.in/items/125586925
【土門蘭デビュー小説】戦争と五人の女
https://hontohitsuji.thebase.in/items/73695610